ヤエン釣りは、アオリイカを掛けるための「ヤエン」をラインに沿って送り込むという、他の釣りにはない独特なスタイルを持っています。そして、この釣法の成功を左右するのが、「ヤエン竿(ロッド)」の性能と使い勝手。
アオリイカに違和感を与えないしなやかさ、ヤエン投入時の安定性、そしてやり取りの際のパワーと操作性が求められます。本記事では、2025年最新版のおすすめヤエン竿をご紹介するとともに、失敗しない選び方のコツも解説してまいります。
 TSURI TRENDS編集部
TSURI TRENDS編集部春の大型アオリイカ狙いの場合は、アタリが少ない場合も多いので、その1回のアタリをミスせず確実にとっていきたいところ


ヤエン釣りに適した竿とは?
ヤエン釣りにおいて竿(ロッド)はアオリイカがアジを抱いてからヤエンを投入し、違和感を与えずに寄せて、確実に取り込むまでの一連のプロセスすべてに関わる、非常に重要な役割を果たします。ヤエン釣りに適した竿を使えばバラしが減り、逆に合わない竿を選んでしまうと、アオリイカを逃す原因にもなりかねません。
では、どのような竿が「ヤエン釣りに適した竿」と言えるのでしょうか?ポイントは大きく分けて、3つあります。
- しなやかな調子(テーパーバランス)
ヤエン釣りでは、アジを泳がせてアオリイカに抱かせる「間」がとても重要です。その間、アオリイカに違和感を与えず自然に寄せるには、ロッドが全体的にしなやかに曲がる“胴調子”や“スローテーパー”の竿が適しています。先調子の硬いロッドでは、イカが違和感を覚えてアジを放してしまうことがあるため、ヤエン釣りでは柔らかく、全体で受け止めるような調子の竿が理想です。 - 5メートル前後の長さ
ヤエンをスムーズに滑らせるためには、ある程度のライン角度が必要です。一般的には4.5〜5.3mの長さが適しており、ヤエンがライン上をしっかりと滑りアオリイカまで確実に到達します。短すぎるルアーロッドなどではロッドの角度が浅くなり、ヤエンが届かなかったり滑りにくくなったりするため、ヤエン釣りには不向きです。 - 適切な号数とバットパワー
号数(竿の硬さ)は1.5〜2号が基準です。アジの重みやアオリイカの引きに対応できる強さが必要ですが、あまりに硬すぎるとアタリを弾いてしまいます。また、大型のアオリイカに負けないためには、胴調子でありながらもしっかりとした“バットパワーが求められます。寄せの時に竿が粘ってくれることで、より自然なやり取りができるようになります。
インターライン or アウトガイド:どちらを選ぶ?
ヤエン竿の構造には「インターラインロッド(中通し)」と「アウトガイドロッド(外ガイド)」の2種類があります。
- インターラインはラインが竿の内部を通る構造で、ガイドや竿への糸絡みが少なく風が強い場合やヤエンの初心者向きです。糸絡みが少ないのでヤエン投入時のトラブルが少なく、快適な操作感を得られます。
- アウトガイドは感度・軽さ・操作性に優れ、慣れている方にはこちらの方が細かいアタリを感じ取りやすくなります。ただし、ラインの穂先絡みが起こりやすいため、操作には一定の慣れと注意が必要です。
ヤエン釣りに適した竿とは、「違和感を与えず、確実に寄せて、しっかり取り込める」性能を備えたロッドです。竿選びを正しく行うことで、アオリイカとのやり取りはより楽しくより確実なものになり結果、バラシを減らす事ができます
インターラインロッドのメリット・デメリット


インターラインロッドの最大のメリットは、「穂先へのライン絡み」がほとんど発生しない点にあります。ヤエンを投入する際やアオリイカとのやり取り中にラインが絡むと、大きなストレスになりかねません。インターライン構造であれば、そうしたトラブルが激減し、より安定した釣りが可能になります。
また、風が強い日や足場が不安定な磯場では、ラインコントロールのしやすさが釣果を左右することもあります。そうした状況でも、インターラインは有利に働くことが多いです。
ただし、デメリットとしては「感度がやや劣る」「重量が増しやすい」「ロッド内部に汚れがたまりやすい」などが挙げられます。特に繊細なアタリをとりたい上級者や、軽快な操作感を求める方には、外ガイドロッドのほうが向いているかもしれません。
- ライントラブルが少ない(穂先にラインが絡みにくい)
- ヤエンがスムーズに滑りやすく、投入しやすい
- 見た目がスッキリしており、風の影響を受けにくい
- 初心者でも扱いやすく、安定したやり取りが可能
- ロッド内部に塩やゴミが溜まりやすく、メンテナンスがやや面倒
- 感度はアウトガイドよりやや劣るため、繊細なアタリが取りにくい場合がある
- 内部構造によりロッドが重くなる傾向があり、長時間の手持ちが疲れやすいことも
糸絡みは激減するので、初心者や強風時には圧倒的に使いやすいのが魅力。ロッドが全体的に太く重たいので、感度や操作性は悪くなります。
アウトガイドロッド(外ガイド)のメリット・デメリット


アウトガイドロッド(外ガイド竿)は、軽量かつ感度が高く、アジの動きやアオリイカの微妙なアタリを手元でしっかり感じ取れるのが大きな魅力です。また、飛距離にも優れ、操作性の高さから上級者を中心に人気があります。
一方で、穂先にラインが絡みやすく、慣れないうちはトラブルが発生しやすいのが難点です。さらに、ガイド部分が外付けであるため、破損のリスクが高く、取り扱いには注意が必要です。扱いに慣れれば非常に快適で、繊細なヤエン釣りを楽しめる優れたロッドです。
- 感度が高く繊細に操作できるのでアオリイカに違和感を与えにくい
- 軽量でロッドバランスも良く、操作性に優れる
- ガイドの摩擦が少ないため、飛距離が出やすい
- 穂先にラインが絡みやすく、扱いに注意が必要(特に風が強い日)
- ガイドがむき出しのため、破損しやすく取り扱いに慎重さが求められる
- ライントラブル時は目視での確認・対応が必要
最初こそライン絡みに戸惑うことがあるかもしれませんが、基本操作を覚えれば、その軽さ・感度・操作性の良さは非常に魅力的。インターラインロッドよりも「繊細な釣り」が展開できるので、ヤエンの本質を考えると間違いなくおすすめできるロッドタイプです。
【2025年最新版】おすすめのヤエンロッド10選
インターライン・アウトガイド両タイプからヤエンロッドを厳選紹介!ヤエン釣りにおけるロッド選びは、釣果を大きく左右する重要な要素です。今回は、インターラインロッド(中通し竿)とアウトガイドロッド(外ガイド竿)の両方から、2025年現在のおすすめモデルを厳選して10本ご紹介いたします。釣りスタイルやご自身の経験値に合わせて、ぜひぴったりの一本を見つけてください。
インターラインロッド(中通しタイプ)
アオリワン50ドライ(ダイワ)
ヤエン専用インターラインロッドの最高峰といえる1本。高密度カーボンとVジョイント構造により、抜群の曲がりとパワーを両立しています。特に春の大型アオリイカとのやり取りにおいて、高い実績と信頼性を誇ります。上級者はもちろん、確かなロッド性能を求める中級者にもおすすめです。
アオリスタ H500SI(シマノ)
インターライン構造により、穂先絡みが少なく、扱いやすさに定評があります。胴調子でアオリイカに違和感を与えず、穏やかなやり取りが可能。シマノ独自の「スパイラルX」による高いねじれ剛性も魅力で、手持ちスタイルにも適応できるバランスの良い一本です。
インターライン リーガルアオリ 1.5-53(ダイワ)
1万円以下で購入できる、コストパフォーマンスに優れたインターラインロッド。入門モデルながら、撥水加工とリニア構造によりスムーズなライン放出が可能で、初めてのヤエン釣りにも安心して使えます。軽量で取り回しも良好です。
IGハイスピード アペルト 1.5号 520A(シマノ)
内部の滑り性能を高めた「ハイパーリペル」仕様のインターラインモデル。ライン抜けが良く、PEラインとの相性も抜群。ホワイト塗装の穂先が視認性を高め、初心者でもアタリをとりやすいのが特徴です。
アウトガイドロッド(外ガイドタイプ)
ボーダレス 4.6MH(シマノ)
磯竿やルアーロッドの枠を超えた“フリースタイルロッド”。ヤエン釣りでの使用実績も多く、非常にバランスの取れたレギュラーテーパー設計。しなやかさとパワーを兼ね備えた1本で、初心者から上級者まで幅広く対応できます。ヤエン以外の釣りにも流用可能なのが魅力です。
ボーダレス BB 4.6MH(シマノ)
ボーダレスの廉価モデルながら、パワーと操作性を両立。少し硬めの設計ですが、4kgクラスのアオリイカにも対応可能。穂先からバットまで滑らかに曲がり、違和感を与えず寄せることができます。コスパ重視のアングラーにおすすめです。
フリーギア MX 460TMH(ダイワ)
ダイワのマルチロッド「フリーギア」もヤエン釣りに最適な磯竿です。軽量かつ操作性が良く、バランスの取れた調子は、アジの泳ぎを邪魔せず、アオリイカのアタリも手元にしっかり伝えてくれます。磯・堤防兼用で使いたい方におすすめ。
リバティクラブ アオリイカ 2-51(ダイワ)
コストを抑えつつ、しっかりアオリイカを掛けたい方におすすめの入門用ロッド。軽量で視認性の高い白穂先仕様。1万円以下で手に入るリーズナブルな価格ながら、ダイワらしい丁寧な設計が光る1本です。
釣果に差がつく3つのチェックポイント
ヤエン竿の選び方を間違えると、アオリイカに違和感を与えて離される、ヤエンがうまく滑らない、取り込みでバラす…といったトラブルにつながります。ここでは、竿を選ぶ際に注目すべき3つの基本ポイントをご紹介します。
- 長さ:5メートル前後が基準
ヤエン釣りにおける竿の長さは、一般的に4.5〜5.3mが適正とされています。特に堤防や磯からの釣りでは、5m前後の長さが最も使いやすく、ヤエン投入時に適切な角度がつけやすくなります。短すぎる竿ではラインが水面に対して立たず、ヤエンがアオリイカに届くまでに失速してしまうこともあるため、できる限り5m前後を基準に選ぶと安心です。 - 号数:1.5〜2号が汎用性◎
竿の号数(硬さ)は、アジを泳がせる際のしなやかさと、イカを寄せるためのパワーのバランスが重要です。多くのアングラーに支持されているのが、1.5〜2号クラスのロッドです。1.5号はアジが元気に泳ぎやすく、違和感を与えにくいため、春のデカイカにも対応可能。反対に2号クラスになると少し硬さは出ますが、アジのサイズが大きいときや風が強い状況でも安定した操作が可能になります。 - 重さとバランス:数値より“持ち感”を重視
カタログスペックでは「自重」が重要視されがちですが、実際の釣行ではロッドのバランスが非常に重要です。多少重くても、重心が手元にある竿は実際には軽く感じられるため、長時間の釣りでも疲れにくくなります。購入前には、可能であれば使用予定のリールを装着して試し持ちをしてみることをおすすめします。持ち重りやバランス感覚は、カタログ数値だけでは判断できない要素です。
トラブルを防ぐ!穂先絡みの対策と実践テクニック
ヤエン釣りにおいて、特に初心者が悩まされやすいトラブルが「穂先絡み」です。ラインが竿先に巻きつくことで、ヤエン投入がうまくいかず、最悪の場合はアオリイカを逃してしまう原因にもなります。ここでは、インターライン・外ガイド両方に共通する、実戦的な対策法をご紹介します。
ラインをたるませない=トラブル激減
もっとも基本的かつ効果的な方法は、「ラインをたるませないこと」です。ヤエンを投入する際や待機中も、ロッドに軽くテンションをかけておくことで、ラインが暴れて絡むのを防ぐことができます。例えば、スプールエッジに人差し指を軽く当ててテンションを保つ、リールのドラグをわずかに調整する、といった細かい工夫が非常に効果的です。
ロッドを顔の横あたりから垂直下ろしていく
ヤエン投入の際、ロッドを大きく振ってしまうとラインが暴れやすくなります。理想は、自分の顔の横あたりからまっすぐ倒すように意識すると、ロッドとラインが一直線になり、穂先絡みのリスクが軽減されます。
インターラインロッドは日常的なメンテナンスが重要
インターラインロッドは絡みには強いものの、内部に塩や汚れが溜まるとラインの滑りが悪くなり、トラブルの原因となることがあります。使用後は真水で内部をしっかり洗い流し、定期的にメンテナンスを行うことで快適な使用感を長く保てます。
アウトガイド派にも朗報:少しの工夫で絡みは防げる
アウトガイドロッドを使用する場合でも、上記の「ラインを張る」「真っ直ぐ倒す」操作を意識することで、穂先絡みを回避できます。慣れてくるインターラインロッドより感度や軽さの面で快適に感じられるという声も多く聞かれます。
まとめ:自分の釣りスタイルに合った一本を選ぼう


ヤエン釣り用ロッドは、快適さと釣果を左右する大切な道具です。インターラインロッドは、ラインの絡みが少なくヤエンの投入もスムーズで、初めての方でも安心して使える点が魅力です。扱いやすさを重視するなら、最初の1本として非常におすすめです。
一方、アウトガイドロッドは軽くて感度が高く扱いやすいので、細かな違和感を感じやすく、また繊細にアオリイカを寄せてくるのに適しているなど慣れてきたアングラーに選ばれています。
どちらが優れているというより、自分の経験値や釣りスタイルに合ったロッドを選ぶことで、ヤエン釣りはもっと楽しく確実にステップアップできます!







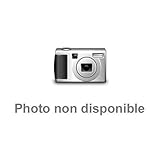





コメント